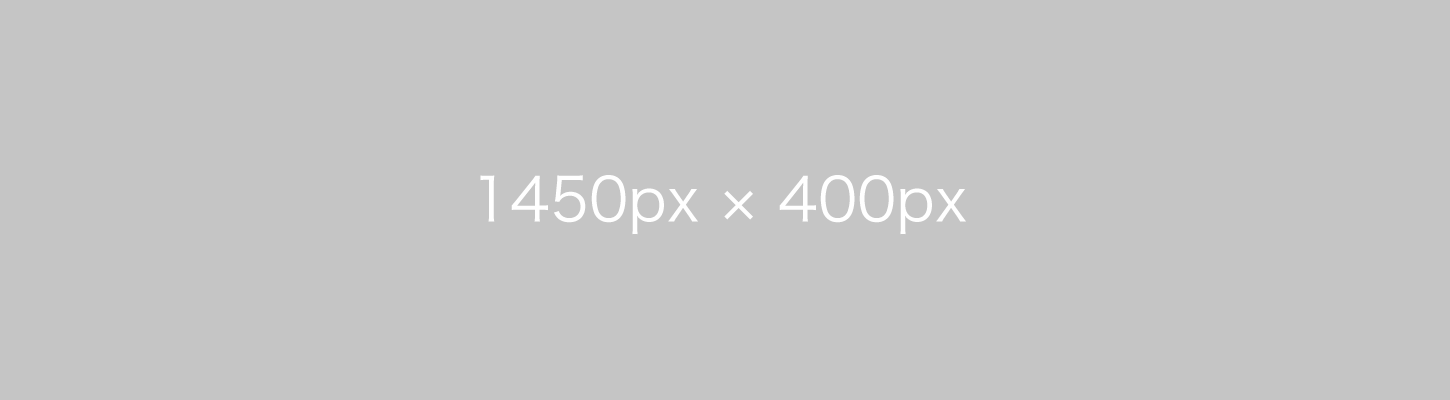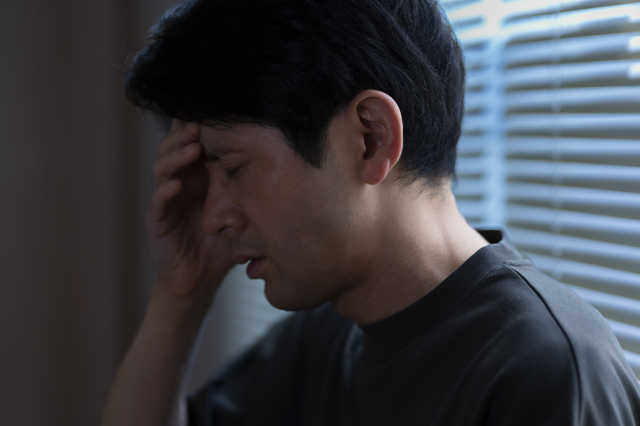睡眠不足は、心の安定に深く関わる「神経伝達物質」のバランスを大きく乱します。特に、幸福感や安心感をもたらすセロトニン、意欲や達成感を生み出すドーパミンは、睡眠中にその働きが調整されます。しかし睡眠が不足すると、これらの物質が適切に分泌されず、心の安定を保ちにくくなるのです。その結果、理由がはっきりしなくても漠然とした不安に襲われたり、気分が落ち込みやすくなったりします。
また、睡眠不足はストレスホルモンであるコルチゾールを増加させます。コルチゾールが過剰に分泌されると、自律神経の交感神経が優位になり、常に緊張状態に置かれるような感覚が続きます。そのため「心が休まらない」「不安が消えない」という状態に陥りやすいのです。
さらに、慢性的な睡眠不足は脳の「扁桃体」が過敏に反応する原因にもなります。扁桃体は恐怖や不安を感じ取るセンサーのような働きをしていますが、睡眠不足の状態ではこのセンサーが壊れた警報器のように過剰に反応し、必要以上に不安を感じさせてしまうのです。
こうした不安感や気分の落ち込みは、本人にとって非常に強いペインです。まず、何をしていても心が晴れず、楽しみを感じにくくなります。また「自分はダメだ」「このままでは良くならない」といった否定的な思考に囚われやすくなり、日常生活のあらゆる場面で行動力を奪われます。人間関係でも、相手の言動を過敏に受け止めたり、対人不安が強まったりして孤立感を深めることもあります。
特に厄介なのは、睡眠不足による不安や落ち込みが、再び睡眠を妨げる悪循環を生むことです。不安でなかなか眠れない → 眠れないことでさらに不安が増す、という負のスパイラルに陥る人も少なくありません。
このように、不安感や気分の落ち込みは「心の平穏」を奪うだけでなく、人生の質そのものを大きく下げるため、解決したいと願う方が多くいらっしゃいます。